電話でお問い合わせ
営業時間:平日9:00〜18:00

無料相談する
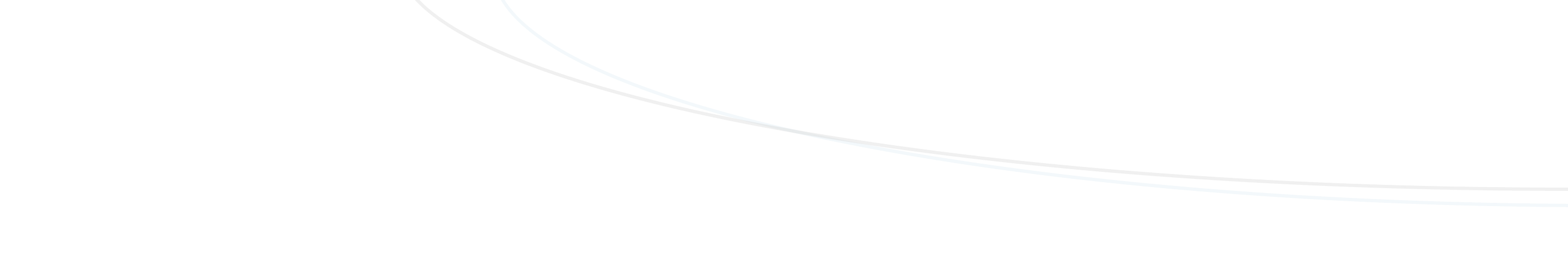
SERVICE
信託とは、ごく簡単にいうと「信じて託す」との文言のとおり「自分の財産を誰かに預けて有効活用してもらい、そこから得られた利益を自分(または自分が指定した人)が受け取る方法」のことです。

信託銀行や信託会社が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。
信託銀行等の受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託で、信託業法の制約の下、信託銀行や信託会社が行うものになります。
商事信託には、投資商品としての「投資信託」、また厳密にいうと信託ではないのですが、信託銀行等の“遺言公正証書作成コンサルティング+遺言書保管+遺言執行”までを行うことをまとめて商品とした「遺言信託」があります。
商事信託とは反対に、受託者が信託報酬を得ないで行う信託です。
財産の所有者の家族や親族など信頼できる人が財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。
そのなかで、家族が受託者となる場合を「家族信託」、障碍を抱える子の生涯資産管理を目的とする場合を「福祉信託」、個人が受託者であるために呼び名が派生した「個人信託」、それら呼び方こそ違いますが、いずれも「民事信託」です。
平成19年から施行されている新信託法のもとでは、営利を目的としない形(民事信託)なら信託業者以外の人が受託者となることができるようになりました。
近年、新たな相続の方法として民事信託が注目され始めたのは、この新信託法の施行がきっかけといえます。
上記の特徴を踏まえ、これからの財産管理の一手法として利用が期待できます。
具体的には、認知症対策(認知症等による資産凍結回避策)や事業承継、倒産対策等、幅広く活用が期待できます。
家庭裁判所の監督のもと資産管理を行うため安全
実際に認知症になるまでは、成年後見の形をスタートすることができない
裁判所を通して手続きを行うので、柔軟な資産運用が難しい
金額の大きい財産を移転するときには、その都度家庭裁判所の許可が必要になる
信託契約で財産運用を定めるため、柔軟に財産の使い道の指定が可能
受任者の能力が問われる
所得税の計算上、損益通算ができない
信託に関する判例が少ない
民事信託と成年後見制度は、どちらもそれぞれ一長一短ありますので、事情に応じ、その両方の制度の併用も含め、当事務所が適切に助言いたします。
